お役立ち記事
- ホーム
- お役立ち記事
設備管理・運用改善
2025.9.12
なぜ「現場目線」がカギなのか?これからの設備保全システムに「本当に」求められる6つの要件

「日々の記録は紙やExcelで手間がかかるばかりで、肝心のデータ活用が進まない…」
「ベテラン作業員のノウハウが属人化していて、若手にどう引き継いだらいいのか…」
「急な故障で生産ラインが停止し、その影響度すら正確に把握できていない…」
製造現場の皆様、御社でもこのような課題に日々直面していませんか?
これからの時代、設備保全システムに求められる役割は、単に「機能があること」ではありません。現場のリアルな課題に寄り添い、具体的な「解決策」を提供できるシステム、すなわち「現場の求める要件」を満たすことです。
先日、とある食品製造業のお客様との対話を通じて、私たちは現代の設備保全現場が抱える「共通の悩み」と、それに対して設備保全システムが「どうあるべきか」について深く気づかされました。
本記事では、その対話で浮かび上がった現場の切実な問題点と、これからの設備保全システムに「絶対に」求められる6つの要件について、具体的にご紹介します。御社の現場の未来のために、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
1
【課題】「結局、入力が面倒で使われない」という負のループをどう断ち切るか?
-
多くのシステム導入で失敗する原因の一つが、「入力の複雑さ」です。システムは導入したものの、現場の作業員にとって負担が大きく、結局紙やExcelに戻ってしまう、という話を耳にすることがあります。これからのシステムには、特別なITスキルがなくても、誰もが直感的に、ストレスなく使える「現場目線」の設計が不可欠です。
- 1-1 システムに求められる解決策
-
• 現場の声を直接反映した開発:システム開発は、実際に製造現場を深く理解し、利用者の声をダイレクトに機能に反映させるアプローチが重要です。これにより、「現場で本当に使える」機能が追求されます。
• 多様な入力環境への対応:PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからもブラウザアプリとして入力できる柔軟性が求められます。さらに、将来的には現場での音声入力による履歴検索機能なども、入力負荷軽減の有力な手段として期待されています。

2
【課題】「今の状況が把握しきれない」保全作業の混乱をどうなくすか?
-
「計画保全が大量にある中に突発的な修繕が入ったりして、特にその状況が把握しきれないのが困り事だ」という声は、多くの現場に共通する悩みでしょう。どの作業がどこまで進んでいて、誰が担当しているのかが不透明なままでは、対応の遅れや抜け漏れに繋がりかねません。
- 2-1 システムに求められる解決策
-
• 直感的な「作業ボード」:保全作業をカード形式で一覧管理し、進捗状況や担当者を明確に可視化する機能が求められます。デジタルサイネージ等で共有すれば、現場全員がリアルタイムで最新状況を把握でき、情報共有の遅れによる混乱を防ぎます。
• 突発対応の即時記録:突発的な修繕が発生した場合でも、その場で即座にカードを作成・登録できる機能があれば、緊急対応の抜け漏れを防ぎ、迅速な状況把握を支援します。
• 自動的なステータス管理:完了した作業はボードから自動的に消え、経過観察や部品待ちの作業は「保留中」へ。期日が来れば再表示されるような機能は、管理の手間を大幅に削減します。
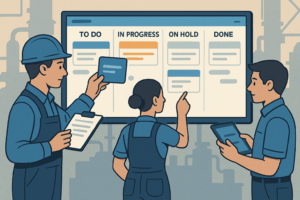
3
【課題】「急な故障でライン停止」という最大のリスクをどう防ぐか?
-
「年間計画を立てるのが大変」「定期点検を見落としがち」といった声は、予防保全の重要性が高まる中で、現場の大きな負担となっています。また、部品の在庫不足が原因で修理が遅れ、生産停止に繋がるリスクも避けたい問題です。
- 3-1 システムに求められる解決策
-
• 確実な計画保全の実行:繰り返し行う計画保全や単発の補修計画を簡単に登録できる機能は必須です。Excel/CSVでの一括登録にも対応していれば、年間計画などの初期設定や入力負担を軽減できます。カレンダー形式やガントチャート形式で進行状況を可視化することで、忘れがちな点検や作業も確実に実施でき、計画的な予防保全を実現します。
• 稼働時間に応じたアラート:お客様からは「稼働時間に応じてアラートを出せますか?」という具体的な要望が寄せられました。点検シートに稼働時間を累積入力し、閾値を超えるとアラートを出す機能は、設備のコンディションに基づいた、より精度の高い予防保全を可能にします。このような機能は多くのシステムベンダーが開発を進めており、今後の標準機能として期待されています。
• 効率的な部品在庫管理:拠点ごとの部品在庫数を正確に管理し、修理記録と在庫が自動的に連動する機能は非常に有効です。発注点管理により部品不足時には自動で通知される仕組みがあれば、部品切れによる生産停止リスクを低減し、無駄な在庫コストも削減できます。

4
【課題】「ベテランのノウハウが失われる」技術継承の壁をどう乗り越えるか?
-
ベテラン作業員の引退や人員流動の中で、熟練のノウハウが失われることは、多くの企業にとって深刻な課題です。「多拠点間で技術レベルに差がある」「若手が過去の事例を参考にしにくい」「拠点ごとに表現が違っても検索できない」といった声も聞かれます。
- 4-1 システムに求められる解決策
-
• 蓄積された履歴の活用:蓄積された保全履歴を横断的に検索可能にし、過去の事例を参考にすることで、問題解決の時間を短縮できる機能は不可欠です。
• AIによるノウハウ継承支援:AIを活用した保全ナビ機能は、異なる拠点での表現の揺れも吸収して類似事例を提示することで、若手従業員のスキルアップ支援や、拠点間の技術格差是正に大きく貢献します。現場でスマートフォンなどから音声入力で過去履歴を検索できる機能があれば、その場での迅速な問題解決と対処時間の短縮につながります。

5
【課題】「感覚的な判断」からどう脱却し、経営に貢献するか?
-
「どの設備にどれくらいのコストがかかっているのか」「故障がどれくらい生産に影響しているのか」といった客観的なデータがなければ、効果的な保全戦略を立てることはできません。特に、製造業では重視されるTPM指標(OEE、MTBF、MTTR)への対応は、生産性向上を目指す上で不可欠な要素です。
- 5-1 システムに求められる解決策
-
• 詳細な分析・改善機能:故障頻度、コスト、停止時間などのデータを多角的に分析し、レポートとして出力できる機能は、経営層や管理職の意思決定を強力に支援します。これにより、どの設備に問題が多く、どの作業にコストや時間がかかっているのかを客観的に把握。効率的な保全計画や設備投資の優先順位付けなど、データに基づいた改善策を立案するための強力な根拠を提供します。
• TPM指標への熱い期待と対応:お客様企業の生産部門責任者様からは、「製造業ではTPM(Total Productive Maintenance)指標(OEE: 設備総合効率, MTBF: 平均故障間隔, MTTR: 平均復旧時間)は重要。停止時間を入力できても、指標化できないなら現場で使えない。停止時間の正確な把握とコスト換算は必須だ」と、その重要性が強く指摘されました。多くのシステムベンダーが、この「標準機能にTPM指標を組み込むこと」を優先課題として開発を進めており、これは多くの製造業が目標とする生産性向上に対し、より高度な指標に基づいた戦略的な意思決定を支援する重要なステップとなるでしょう。

6
【課題】「一度入れたら終わり」のシステムで、変化の激しい現代に対応できるか?
-
市場や技術が絶えず変化する現代において、一度導入したら終わり、というシステムでは不十分です。現場のニーズや技術の進化に合わせて、柔軟に機能を追加・改善していく「進化し続けるサービス」こそが求められています。
- 6-1 システムに求められる解決策
-
• ユーザー要望の迅速な反映:システムは「完成品ではなく、進化し続けるサービス」であるべきです。ユーザー会やメールで寄せられるご要望を短期間(3~6ヶ月単位)で機能改善に反映し、継続的に新しい機能(毎月10~20機能程度)がリリースされる体制が望ましいでしょう。
• 標準機能の開発費は原則無償:導入企業からの要望によって追加される標準機能の開発費は、基本的に無償であるという方針は、多くの企業にとって導入しやすい大きな魅力となります。
• 外部連携への期待:メーカーからの設備情報一括取り込み機能など、具体的な運用に直結する外部連携機能も、今後の開発ロードマップに反映されるべき重要な要件です。

7
まとめ
-
お客様との対話を通じて、これからの設備保全システムは、単なる記録ツールではなく、現場の「困った」に真摯に寄り添い、お客様と共に成長し、課題を解決していく「戦略的パートナー」であることが明確になりました。
もし、御社の現場でも「うちも同じ課題を抱えている」「これらの要件を満たすシステムを探している」と感じたなら、ぜひ一度、ミロクルカルテの「現場目線」を体感し、その可能性を探ってみませんか?
導入事例を見る
資料ダウンロードはこちら(無料)
お問い合わせ・無料トライアルのお申し込みこの記事が、サービス選定をご検討中のご担当者様にとって、少しでも良い参考となれば幸いです。
ご興味があれば、ぜひ一度ミロクルカルテをご覧になってみてください。
お問い合わせ・
ご相談
ご不明点やご質問など、
お気軽にお問い合わせください。
お電話でも承っております。
ミロクルカルテのより詳しい
活用方法や、
実際の運用イメージ
などをご紹介しています。


















